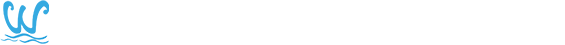編集部の小早川です。
最近になって「ステーブルコイン関連株」が大きな注目を集めています。法改正によってステーブルコインが「電子決済手段」として正式に認められ、フィンテック企業や大手金融機関が続々と参入。市場は熱気を帯びています。
でも、ステーブルコインとは一体何なのでしょうか?どの銘柄が注目すべきか?最近のニュースはどうなっているのか?今回のコラムで解説したいと思います。
ステーブルコインとは何か?
ステーブルコインは、法定通貨(例:日本円や米ドル)や、金などの資産に価値が連動するよう設計されたデジタル通貨で、価格の安定性を目的とした暗号資産です。
ビットコインなどの暗号資産は価格変動が激しい一方、ステーブルコインは1コイン=1円や1ドルといった固定レートを維持することで、決済や送金の利用に適しています。
日本では、2023年6月の改正資金決済法施行により、ステーブルコインは「電子決済手段」とされ、銀行や信託会社による発行が可能となりました。これにより、国内での実用化が加速し、関連企業の株価にも注目が集まっています。
なぜ今、ステーブルコインが注目されているのか?
ステーブルコイン市場は世界的に急拡大しており、2025年8月時点で市場規模は約2,780億ドル(約41兆円)に達しているようです。日本でも同じで、ステーブルコイン関連株が投資家の関心を集めています。
1:規制の明確化と市場参入の活発化
法改正によってステーブルコイン発行が解禁され、金融庁の監督下で信頼性が向上しました。
最近も関連銘柄が上昇しましたが、今年8月にはフィンテック企業JPYCによる日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」が金融庁の承認を受け、秋にも発行開始予定です。
これが国内初の円建てステーブルコインとなり、国際送金や決済での普及が期待されています。
2:米国での規制進展とグローバルな影響
2025年3月、トランプ米大統領がステーブルコインの利活用を促進する大統領令に署名し、米国での規制枠組み「GENIUS法案」が上院で可決しました。
これにより、米ドル連動型ステーブルコイン「USDC」の普及が進む中、日本企業との連携も強化されています。
3:実用化の広がり
ステーブルコインは即時かつ低コストな送金や、その追跡しやすさなどから企業間決済や国際送金、さらには納税など多様な用途で活用が進んでいます。
JPYCは暗号資産投資家がDeFiでの利益を日本円に変換して納税に充てるケースや、鹿島建設が作業員へのインセンティブ付与に活用する実証実験を行っています。
また、ステーブルコインの普及が日本国債への安定的な需要を生むと考えられ、ステーブルコイン発行体が裏付け資産として国債を保有することで、市場の安定化にも寄与する可能性もあります。
注目すべきステーブルコイン関連銘柄
次に、テーブルコイン関連事業に積極的に取り組む日本企業をまとめてみました。
SBIホールディングス(8473)
SBIホールディングスは、ステーブルコイン市場で先行者利益を狙うリーディングカンパニーです。
2023年11月に米Circle社と提携し、米ドル連動型ステーブルコイン「USDC」の日本展開を加速。子会社のSBI VCトレードを通じて、2025年3月から国内初のUSDC一般向け取引を開始しました。
さらに、Circle社への約70億円の出資を発表し、戦略的なパートナーシップを強化。SBIはステーブルコインを活用したレンディングや決済サービスを展開し、デジタル金融のエコシステム構築を目指しています。
最近も米国の「GENIUS法案」可決を受けて、USDCのグローバルな需要拡大が追い風に。SBIはUSDCを活用したレンディングサービスの開始を計画中で、2025年秋のサービス開始が噂されています。
また、SBIの暗号資産取引所は国内シェアトップクラスで、ステーブルコインの流通基盤としての強みを活かし、個人投資家だけでなく機関投資家向けのサービスも拡大中です。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)
三菱UFJ信託銀行が主導するステーブルコイン発行「プログマコイン」は、国内ステーブルコイン市場の標準化を目指す野心的なプロジェクトです。
新会社「株式会社Progmat」は、NTTデータ、みずほFG、三井住友FGと連携し、ステーブルコインのインフラ構築を進めています。プログマコインは、銀行預金や国債を裏付け資産とする円建てステーブルコインの発行を計画し、企業間決済や国際送金での利用を想定。三菱UFJは発行比率49%を占めるリーダー企業として、本命株の位置づけです。
今年7月にはプログマコインを活用した企業間決済の実証実験が成功し、大手商社や製造業での採用が検討されています。三菱UFJはメガバンクとしての資金力と信頼性を武器に、ステーブルコイン市場での主導的地位を確立する可能性が高いです。
プログマコインの商用化が進めば、企業向け金融サービスの新たな収益源となるでしょう。ただし、大型株ゆえに値動きは緩やかで、短期的な爆発力には欠けるかもしれません。
三井住友フィナンシャルグループ(8316)
続いてもメガバンクから三井住友銀行です。、2025年3月からTIS、Labs、Lireblocksと共同で、ステーブルコインの事業化に向けた検討を開始しました。
貿易決済や国際送金での利用を考えており、さらにプログマコインの共同事業にも参画し、ステーブルコインの標準化と普及を後押ししています。
今年5月、SMBC日興証券がステーブルコインを活用した資産運用商品の開発を検討中と報じられ、投資家層の拡大が期待されています。さらに、国際送金コストの削減を目指した実験が進行中で、2026年中の商用化を目指しています。
三井住友は、三菱UFJと並ぶメガバンクとして、ステーブルコイン市場での競争力が高いです。プログマコインの共同事業に加え、独自の取り組みも進めており、金融インフラのデジタル化における存在感が増しています。株価は安定感があり、中長期投資向けと言えるでしょう。
アステリア(3853)
アステリアは、JPYC株式会社に出資して日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」の普及を支援しています。
JPYCは法的には「前払式支払手段」として扱われますが、DeFiでの資産運用や納税、企業間決済での利用が拡大中。アステリアはブロックチェーンを活用したデータ連携技術で知られ、JPYCのインフラ構築にも貢献しています。
2025年8月、JPYCが金融庁の資金移動業登録を完了し、秋にも国内初の円建てステーブルコインを発行予定です。
流通額は30億円を突破し、1兆円規模を目指すとの発表が株価上昇の材料に。鹿島建設との実証実験では作業員へのインセンティブ付与にJPYCを活用し、建設業界での新たなユースケースが注目されています。
アステリアは時価総額が小さい中小型株。ステーブルコイン関連のニュースに敏感に反応するテーマ株です。JPYCの普及が進むほど株価のアップサイドが期待されますが、ボラティリティが高い点に注意が必要です。
東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)
東京きらぼしも、ふくおかFG傘下の「みんなの銀行」や四国銀行と共同で、2023年3月からステーブルコインの発行に向けた実証実験を開始。地域経済の活性化や低コスト送金を目的とした取り組みが特徴です。
今年4月、地域中小企業向けのステーブルコイン決済プラットフォームの試作が完了。地銀としては珍しくステーブルコイン分野で積極的な姿勢を見せています。2025年後半には、観光業や地元商店街での決済実証も計画中。
規模は小さいものの、ニッチな市場での活用が期待されるため、テーマ株としてのポテンシャルがあります。地域密着型のビジネスモデルが投資家の関心を集める可能性も。
インタートレード(3747)
インタートレードは三井物産デジタルコモディティーズが発行する金価格連動型ステーブルコイン「ジパングコイン」の取引システムを提供。ステーブルコインのインフラ支援を通じて、市場参入を果たしています。
金価格の高騰が続く中、ジパングコインの需要が増加。2025年7月にインタートレードがジパングコインの取引量増加に伴うシステム拡張契約を獲得し、株価が急騰しました。
時価総額が小さいため、短期的な値動きが期待されるテーマ株です。金担保型ステーブルコインのニッチな市場での成長余地は大きいですが、競合他社の動向や金価格の変動に影響を受けやすい点に留意が必要です。
シンプレクス(4373)
JPYCにステーブルコインの取引・管理システムを提供し、発行と流通のインフラを支えています。シンプレクスは金融機関向けのシステム開発で実績があり、ステーブルコインの技術基盤としての役割が期待されます。
最近もJPYCの金融庁承認を受け、シンプレクスが提供するシステムの信頼性が評価され、新規契約の獲得が報じられています。JPYCの流通拡大に伴い、システム需要が増加中。
JPYCの成長とともに、シンプレクスのシステム需要が拡大する可能性が高いです。中小型株ながら安定した技術力を持つ企業として、中長期的な成長が期待されます。
GMOインターネットグループ(9449)
日本円連動型「GYEN」や米ドル連動型「ZUSD」を提供するなど、GMOは暗号資産取引所や決済事業で国内トップクラスの実績を持ち、ステーブルコインを活用したグローバル展開を進めています。
今年6月にはGYENの国際送金での利用が拡大し、アジア地域の金融機関との連携を強化。Solanaネットワークの高速性と低コストを活かし、競争力を高めています。
GMOの暗号資産事業のノウハウはステーブルコイン市場での強み。グローバルな需要に対応する展開力が、株価の成長を後押しするでしょう。
オリックス(8591)
オリックス銀行が2023年9月、G.U.Technologiesと共同でステーブルコイン発行の実証実験を開始。地域経済や中小企業向けの決済手段としての活用を模索しています。
5月には実証実験の第2フェーズとして、中小企業向けの低コスト送金サービスを試験運用。2026年中の商用化を目指しています。
オリックスの多角化戦略とステーブルコインのシナジーが期待されますが、実験段階のため、短期的な株価への影響は限定的かもしれません。
ソニーグループ(6758)
ソニー銀行が2024年4月からステーブルコイン発行の実証実験を開始。ゲームやスポーツ分野での決済手段としての活用を検討し、ソニーグループのコンテンツ事業との連携を模索しています。
すでに先月、ソニーのNFTプラットフォームとステーブルコインを組み合わせた決済システムのプロトタイプを公開。ゲーム内経済やファンエンゲージメントでの活用が注目されています。
ソニーのブランド力とコンテンツ事業とのシナジーは、ステーブルコインの新たなユースケースを生み出す可能性が高いです。長期投資向けの銘柄として注目です。
投資のポイントとリスク
ステーブルコイン市場は世界で2,780億ドル超と急拡大中。日本でも企業間決済や国際送金での利用が広がり、関連銘柄の成長が期待されます。
SBIや三菱UFJFGは安定感があり、アステリアやインタートレードは短期的な値動きを狙うテーマ株として魅力的です。日本や米国の規制進展が株価に大きく影響するため、最新情報をチェックしましょう。
JPYCの金融庁承認、SBIのUSDC展開、プログマコインの進展など、2025年は市場の飛躍の年になりそうです。
ステーブルコインの普及はデジタル金融の新たな可能性を開く可能性を秘めており、投資家にとって見逃せないテーマです。私もこの動向から目が離せません。投資を検討するなら、企業ごとの取り組みと規制動向をしっかり見極めましょう。