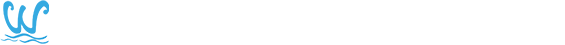編集部の黒木です。
来週末に迫った総裁選挙、結果がわかるまであと1週間となりました。先日は小泉総理が誕生した時に注目したい銘柄を解説しましたが、今回はその続編となる「高市総理で注目したい銘柄」についてまとめました。
高市さんのカラーは「経済安全保障」です。サイバーや宇宙といった新たな安全保障、そして国家の未来を左右する先端技術への「成長投資」という、この2つを両輪として日本の経済と安全にフォーカスした政策が多いです。
今回取り上げたのがこちらの4社です。
FFRIセキュリティ(3692)
QPS研究所(5595)
ジェイテック・コーポレーション(3446)
助川電気工業(7711)
それぞれ見ていきましょう。
総裁選前の背景
高市さんは、第2次安倍内閣で「アベノミクス」を進める立場にいました。経済安全保障大臣として、サプライチェーン強化やインフラの安全性確保のための法整備も進めました。
今回の総裁選では、防衛費の増額、サイバーセキュリティ庁の創設、未来のエネルギー覇権を握るための核融合開発への投資などを公約に掲げています。
また、防衛セクターは”高市銘柄”と言えますが、中心銘柄は以前にまとめたコラムをご覧ください。
【第1弾】日本の防衛株銘柄4選。地政学リスクが高まり世界的な注目セクター
【第2弾】注目の防衛株4選。世界的な防衛トレンドの波に乗っていきましょう
(1) FFRIセキュリティ(3692):サイバー防衛の国産の砦
FFRIセキュリティは、2007年に設立された日本のサイバーセキュリティ業界では草分け的な存在です。
官公庁やインフラ企業を顧客に持つサイバーセキュリティの専門企業で、ウイルス対策ソフトの会社ではなく、国家安全保障のレベルで見えない攻撃から守る「防人」のような存在です。
強みは次世代型のエンドポイントセキュリティ技術で、巧妙化するサイバー攻撃に対して後追いではない先回りした防御を可能にします。
高市さんの考え方としては、国家の基幹システムを海外の技術に依存することへの危機感があります。サイバー防衛という国家の重要な要素を外国に任せるのではなく、純国産の独自技術を持つことの大切さを重視しており、今後も注目されそうな企業です。
ビジネスモデルは、ソフトウェアを売り切るのではなく、年間ライセンスで使用料を得るサブスク型で、顧客が増えるほど収益が安定的に積み上がるストック型のビジネスであり、投資家からの評価も高いです。
政府の情報システムを強化し、国産技術を重視する方針が明確になれば、飛躍的に拡大するかもしれません。
サイバーセキュリティ業界は技術革新のスピードが速く、常に研究開発への投資が必要です。米国のクラウドストライク社のような海外の巨大企業との競争は激しく、技術の進歩が今後も課題となるでしょう。
(2) QPS研究所(5595):宇宙から日本を守る「天空の目」
QPS研究所は、九州大学での20年以上にわたる小型衛星の研究を経て、2005年に創業されました。
「宇宙の可能性を広げ、人類の発展に貢献する」という壮大なビジョンを掲げる、日本を代表する宇宙スタートアップ企業です。
独自開発の軽量で大きな「展開式アンテナ」が特徴で、重さ100kg台の小型衛星ですが海外の1トン級の大型衛星にも引けを取らない世界トップクラスの解像度(46cm)を達成しています。
メイン事業は衛星から取得したSAR画像の販売ですが、目指すのはその先の世界で、取得したデータをAIで解析し、「地盤沈下監視サービス」や「インフラ老朽化検知サービス」といった、特定の課題を解決するためのソリューションとして提供することを目指しています。
これが実現すれば、単なる画像販売よりもはるかに高い付加価値を生み出すことができます。
高市さんの政策では、安全保障だけでなく防災面にも力を入れており、同社の技術が恩恵を受ける可能性もあります。ただ、こうした宇宙事業は莫大な資金が必要で、現在は、衛星網の構築のための巨額の先行投資が続くフェーズであり、赤字経営が続いています。
ロケットの打ち上げ失敗や、軌道上での衛星の故障といったリスクも常に伴うため、少しリスクが高い投資になるかもしれませんが、将来への期待からも注目したい銘柄の1つです。
(3) ジェイテック・コーポレーション(3446):未来を創る超精密技術
ジェイテックは理化学研究所発のベンチャーとして1993年に設立されました。
大型放射光施設「SPring-8」などで使われる、超高精度の実験装置や測定機器をオーダーメイドで開発・製造する技術者集団とも言えるでしょう。
研究者の「こんな測定がしたい」「こんな実験がしたい」という要求に対して、独自の装置を設計・製造する受注生産がメイン事業です。
超高真空技術や極低温技術、超精密加工技術などを組み合わせ、ナノメートル(10億分の1メートル)単位の精度を実現する、その「究極のものづくり」が強みです。
フランスで建設中の核融合実験炉でも活かされており、この実験炉の心臓部とも言えるプラズマ計測装置の重要部品を開発・製造しており、日本の技術力の高さを世界に広めています。
日本は製造業の国ですから、科学技術への予算の増額も必要だと思います。同社は大学や国の研究機関がクライアントであり、予算が増加することでこれらのクライアントからの受注増加も見込まれます。
先端科学の発展にジェイテックの技術は不可欠であり、日本の研究開発を支える企業とも言えるでしょう。
国の研究開発予算の動向に業績が左右されやすいのがデメリットで、売上が特定の大型案件に依存する傾向でもあります。しかし、その参入障壁の高さと技術的な優位性が強みです。
(4) 助川電気工業(7711):「熱」を制する「匠の技」
助川電気工業は1945年の創業以来、「熱」というテーマ一筋に技術を磨き続けてきた企業です。
日本の原子力産業の初期から特殊なヒーターやセンサーを開発し続け、原子力分野の熱制御において国内随一のノウハウを蓄積してきました。
事業は①原子力関連、②半導体・その他産業、③研究開発、の3本柱で構成され、原子力分野で培った高温・高圧・高放射線量などの技術を半導体製造装置や医療機器といった他分野に応用しています。
そして、その技術をさらに転用させ、核融合分野に進出しており、核融合実験炉「ITER」では真空容器内をクリーンに保つための「ベーキングヒーター」を世界で初めて開発しました。
また、核融合炉の熱を取り出す「ブランケット」の開発も手がけるなど、その技術力が世界から評価されています。
まさに「成長投資」と「エネルギー安全保障」の中心とも言える企業で、核融合というテーマに携わりつつも、既存の事業で安定した収益と利益を上げているのも強みです。
先ほどのQPS研究所のようなベンチャー企業とは少し異なりますね。核融合の実用化が数十年単位の長期的なテーマであり、社会のエネルギー政策への動向にも影響されるため、中長期で見ておきたい銘柄と言えるでしょう。
まとめ:日本の技術を世界へ
今回取り上げた4社は、それぞれが異なる分野ですが、「日本の技術を世界へ」という点で一致しています。
高市さんの政策テーマである経済安全保障は、まさにこれらの企業が中心となっています。いずれも参入障壁が高く、他社が簡単にマネできない技術を持っており、国家戦略とも深く結びついています。
総裁選の行方はまだわかりませんが、「経済安全保障」というテーマは誰が総理になっても同じだと思います。日本の国家戦略の中心であり続けるでしょう。
ご紹介した4社が日本の未来を技術で支える重要なプレーヤーであることは間違いありません。日本の進むべき道を考える上でも、これらの企業の動向に注目していく価値は高いと考えています。
【免責事項】
この記事は、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。ご紹介した情報は政策の動向や市場環境によって変化する可能性があります。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。