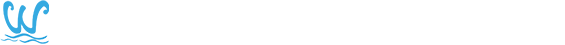編集部の黒木です。
今月は日米ともに重要な決算が続きましたが、日本経済を牽引する自動車産業から衝撃的なニュースが飛び込んできました。
国内自動車大手7社の2025年度第2四半期(4-9月期)の決算が出ましたが、その内容は「惨状」と呼ぶにふさわしいものでした。
7社のうち、実に3社が最終赤字に転落。黒字を確保した企業も軒並み大幅な減益となり、業界全体が深い苦境に立たされていることが鮮明になりました。
最大の要因は何か?答えは明確です。米政権による高関税、いわゆる「関税ショック」です。今回の決算で7社が負担した関税の総額は、一部報道によれば4-9月期だけで実に1兆4000億円を超える規模になるようです。
各社が血のにじむようなコスト削減や販売努力で積み上げてきた利益を、一瞬で吹き飛ばすほどで、7社全体の純損益(最終利益)の合計は、前年同期と比べて約7,827億円も減少。
日本経済の屋台骨である自動車産業が大きく揺らいでいることを示す数字と言えるでしょう。そこで本コラムでは、「関税ショック」が日本企業に何をもたらしているのかを分析していきます。
深刻な「本業赤字」と、5年ぶりの転落
まず、深刻な状況に陥った赤字転落組の3社を見ていきます。
最も厳しい結果となったのが日産自動車です。最終損益は約2,219億円の赤字となりました。売上から原価や販管費を引いた「本業の儲け」を示す営業損益ベースで、すでに約276億円の赤字に陥っています。
これは、米国での追加関税が約1,497億円もの減益要因として直撃したことが大きいです。本業で利益を出せないという事態は、企業の存続基盤そのものが脅かされていると言っていいでしょう。
次に続くのがマツダで、約452億円の最終赤字になりました。実に5年ぶりとなる最終赤字です。そして三菱自動車も、約92億円の最終赤字となりました。三菱自動車はかねてより苦戦していた東南アジアや北米での販売不振に加え、関税という「追い打ち」を受けた格好となり、苦しい経営が続いているようです。
この3社に共通するのは、関税という巨大なコスト負担増を、自社の企業努力だけではもはや吸収しきれなくなったという現実です。
「勝ち組」トヨタにも重くのしかかる9,000億円の足枷
一方で、黒字を確保した4社も、決して安泰ではありません。内訳を見れば、彼らがいかに「傷だらけの黒字」を確保したかが分かります。
「絶対王者」トヨタ自動車は、約1兆7,734億円という巨額の純利益を発表しました。一見すると、その強さは揺るがないように見えます。
しかし、内情は深刻で、トヨタが上期だけで受けた関税の影響は、営業減益要因として実に約9,000億円に上ると試算されています。
つまり、もし関税という「足枷」がなければ、トヨタの利益は今期、異次元のレベルに達していた可能性があったのです。稼ぎ頭であるトヨタからこれほど巨額の利益が失われたことは、日本の税収や経済全体にとっても大きな損失です。結果として、トヨタの純利益も前年同期比で7.0%の減益となりました。
ホンダ純利益こそ約3,118億円を確保したものの、前年同期比では37.0%減という大幅な減益になりました。
スバルは純利益約904億円に対し、前年同期比で44.5%減とほぼ半減に近い落ち込みです。特にスバルは北米市場への依存度が高いため、関税の影響を真正面から受けた形となりました。
好調だったスズキも例外ではありません。純利益約1,927億円は素晴らしいですが、前年同期比では11.3%の減益です。関税や原材料高に加え、好調だったはずの主力市場・インドでの販売減速も響いています。
「地政学リスク」
これは、単なる「業績の悪化」ではありません。「地政学リスク」が企業経営のハードルになったことが懸念です。
これまで自動車メーカーの業績は、為替レートや販売台数で説明ができました。しかし、今や「米中対立」「保護主義政策」などの政治要因で一瞬にして1兆円を超えるコストを発生させる時代になったのです。
自社の努力ではコントロール不可能な「関税」という名のコストを、どうヘッジしていくのか。生産拠点の見直しや、場合によっては政治リスクそのものを見直すという重い経営判断を迫られています。
また、自動車業界は今、EV(電気自動車)、自動運転、コネクテッドといった「CASE」と呼ばれる100年に一度の大変革期の真っ只中にいます。
この競争を勝ち抜くには、年間数千億円から兆円単位の研究開発費が必要です。しかし、今回のように関税によって巨額のキャッシュフローが外部に流出してしまえば、未来への投資が滞ることは避けられないでしょう。
目先の利益が失われるだけでなく、中長期的な競争力そのものが削がれているのです。関税ショックが長引けば長引くほど、日本の自動車メーカーは世界的な開発競争から脱落していくリスクが高まります。
構造転換を迫られる自動車業界
2025年度の上期決算は、自動車産業が自社の努力だけではどうにもならない巨大な構造変化の波に直面していることが鮮明になりました。
もはや、優れた製品を日本で作り、輸出するという従来の成功方程式は通用しなくなっているのかもしれません。
理不尽とも言えるコスト増を前提とした上で、サプライチェーンの再構築、販売戦略の抜本的な見直し、そして政治とどう向き合っていくかという高度な戦略を早急に固めなければなりません。
通期(2026年3月期)の見通しは、多くの企業が「未定」あるいは「下方修正」を余儀なくされるでしょう。自動車産業の苦境は、部品メーカーや素材産業、ひいては日本経済全体の冬の時代の始まりを告げているのかもしれないーー。そうした懸念も出てくると思います。
各社の経営陣が、この未曾有の危機にどう立ち向かうのか。その手腕が今、問われているのです。